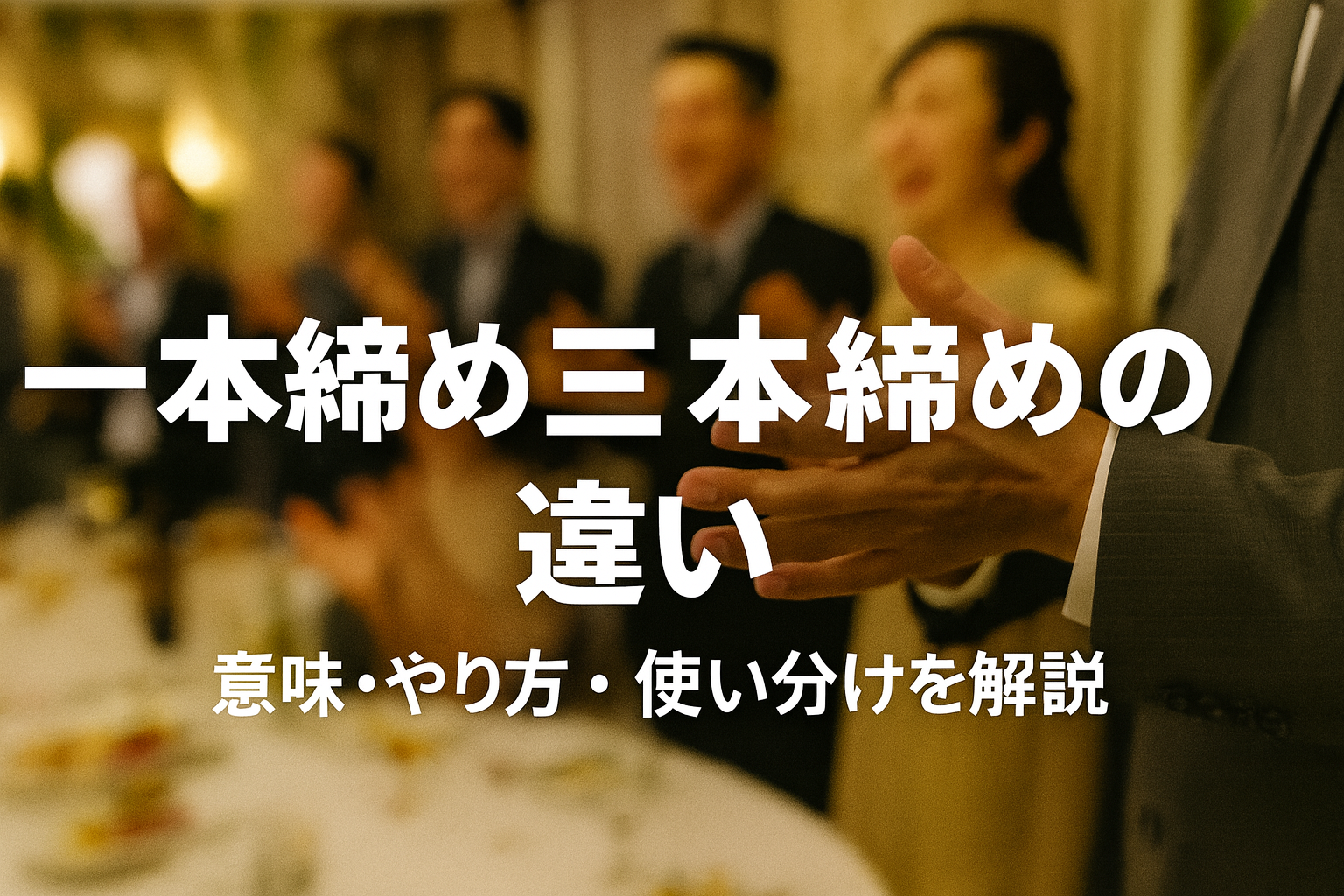【徹底解説】一本締めと三本締めの違いとは?意味・由来・正しいやり方までわかりやすく解説
会社の締め会、地域の行事、忘年会、結婚式の披露宴など、日本のさまざまな場面で「締め」の拍手が行われます。
しかし、
- 一本締めと一丁締めって違うの?
- 三本締めってどうやるの?
- どんな場面でどちらを使うのが正解?
- 関東と関西で違うって本当?
と疑問を持つ方も多いはずです。
この記事では、一本締めと三本締めの違いを、意味・歴史・場面別の使い方・正しい手順まで、初心者にもわかりやすく解説します。
「今日の締め、お願いできますか?」と急に振られても安心できるよう、この記事でしっかり押さえておきましょう。
一本締めと三本締めの違いを一言で言うと?
まず最初に結論から整理しておきます。
一本締めとは?
「三本締めの最後の1回だけを行う簡略版」です。リズムは、
チャチャチャ、チャチャチャ、チャチャチャ、チャッ!
という一連の拍手を1回だけ行います。
三本締めとは?
一本締め(一丁締め)の一連の拍手を3回繰り返し、最後にもう一度一本締めを行う正式バージョンです。
つまり、
- 三本締め:正式・丁寧に締めたいとき
- 一本締め:簡略してサッと締めたいとき
という使い分けになります。
一本締めの意味と特徴
一本締めは本来「一丁締め」
一般的には「一本締め」と呼ばれていますが、元々は「一丁締め(いっちょうじめ)」が正式な名称です。現在は、ほぼ同じ意味として使われています。
一本締めのリズム
拍手の基本リズムは次のとおりです。
チャチャチャ、チャチャチャ、チャチャチャ、チャッ!
3回×3拍+最後に「チャッ!」で締めます。テンポよく揃うと、とても気持ちよく場がまとまります。
一本締めが使われる場面
- 部署単位の飲み会や少人数の打ち上げ
- 仕事の一区切りをつける小さな会合
- 時間が押していて、簡潔に締めたいとき
- カジュアルな集まり・懇親会
形式よりも「サッとまとまりたい」場で使われることが多いのが一本締めです。
三本締めの意味と特徴
三本締めとは?
三本締めは、一本締め(一丁締め)を3回繰り返し、最後にもう一度一本締めで締める方式です。江戸時代の商人や職人の文化が由来と言われており、今でも式典などで使われています。
三本締めのリズム
1回分のリズムは、やはり
チャチャチャ、チャチャチャ、チャチャチャ、チャッ!
これを3回繰り返し、さらに最後に一本締めを行います。掛け声を挟みながら行うことで、場に一体感が生まれます。
三本締めが使われる場面
- 会社の創立記念パーティーや大規模な式典
- 結婚披露宴や記念行事
- 地域の大きなイベントの締め
- 複数団体が集まる公式な会合
一本締めと比べて時間はかかりますが、そのぶん丁寧で重みのある締めになります。
一本締めと三本締めの違いを表で整理
| 項目 | 一本締め(=一丁締め) | 三本締め |
|---|---|---|
| 回数 | 一連の拍手を1回だけ | 一連の拍手を3回+最後に1回 |
| 所要時間 | 数秒で終わる | 15〜20秒ほどかかる |
| 格式 | カジュアル・簡易 | フォーマル・丁寧 |
| 主な場面 | 飲み会・小規模な集まり | 式典・披露宴・大規模イベント |
| 目的 | 手早く場を締める | 盛大に、区切りをはっきり示す |
一本締めのやり方(掛け声付き)
ここからは、実際に前に立って仕切るときに困らないよう、一本締めの具体的な流れを紹介します。
一本締めの手順
- 締めの挨拶をする(会の感謝・今後の一言など)
- 「それでは、一本締めでお願い致します」と宣言する
- 参加者全員に立ってもらい、軽く手を前に構えてもらう
- 「お手を拝借。よーっ!」と掛け声をかける
- 間を少し置いて、みんなで
チャチャチャ、チャチャチャ、チャチャチャ、チャッ!
ポイントは「よーっ!」のあとに半拍〜一拍ほど間を置くことです。間を取ることで全員のタイミングが揃いやすくなります。
三本締めのやり方(掛け声付き)
つづいて、三本締めの具体的な流れです。一本締めを3回繰り返すだけですが、掛け声の入れ方で分かりやすさが変わります。
三本締めの手順
- 締めの挨拶をする
- 「それでは、三本締めで締めたいと思います」と宣言する
- 全員に起立してもらい、手を構える
- 「お手を拝借。よーっ!」で1回目
チャチャチャ、チャチャチャ、チャチャチャ、チャッ! - 「よっ!」で2回目
チャチャチャ、チャチャチャ、チャチャチャ、チャッ! - 「よっ!」で3回目
チャチャチャ、チャチャチャ、チャチャチャ、チャッ! - 最後に「それでは、最後にもう一度。よーっ!」で一本締め
チャチャチャ、チャチャチャ、チャチャチャ、チャッ!
掛け声を挟むことでリズムが崩れにくくなり、参加者も「今が何回目か」を把握しやすくなります。
関東と関西で違う?地域差の豆知識
一本締め・三本締めは、もともと江戸(関東)の文化と言われています。そのため、関東では比較的正式な手順が残っており、
- 一丁締め(一本締め)
- 三本締め
が明確に区別されていることが多いです。
一方、関西では型にこだわらないことも多く、拍手を何度か揃えて「パンパンパン、パン!」と締めるなど、場のノリや雰囲気を重視する文化もあります。
全国から人が集まる場では、事前に「一本締めで行きます」「三本締めでお願いします」と口頭で説明してから始めると、誤解が少なくなります。
一本締めは間違われやすい?「一丁締め」との関係
多くの人が「一本締め」と呼んでいるものは、本来は「一丁締め」が正式名称と言われています。ただし、現代ではほぼ同じ意味で使われているため、日常の場面ではそこまで神経質になる必要はありません。
- 一本締め:口語的な呼び名。一般的によく使われる
- 一丁締め:本来の正式な呼び方。式典などで使われることも
フォーマルな場であれば、「一丁締めで締めたいと思います」と言うと、少し通っぽく、きちんとした印象になります。
どっちを使えばいい?シーン別の使い分けガイド
フォーマルな場(会社式典・結婚式など)
会社の創立記念パーティーや結婚披露宴など、格式やきちんと感が求められる場では三本締めが向いています。場全体の一体感が生まれ、「今日の会がしっかり締まった」という印象を残すことができます。
カジュアルな場(飲み会・打ち上げなど)
部署の飲み会、仲間内の打ち上げなどでは、一本締め(=一丁締め)で十分です。短時間でスパッと締められるので、会の雰囲気を崩さずに解散へ移れます。
時間が押しているとき
幹事として進行していると、「時間が押してしまった」という場面もあります。そんなときは、一本締めでコンパクトに締めるのが現実的です。
複数の団体が参加する大きなイベント
参加者が多く、いくつもの団体が関わるイベントでは、三本締めのほうが「きちんとした締め」になり、主催者の印象も良くなります。
一本締め・三本締めの注意点
① 直前にやり方を軽く説明する
若い世代や外国人が多い場では、そもそも一本締め・三本締めを知らない人もいます。
「それでは、私の『よーっ!』の合図に合わせて、チャチャチャ…と3回+最後に1回でお願いします」と簡単に説明してから始めると、きれいに揃いやすくなります。
② 掛け声と「間」を大事にする
掛け声のあと、すぐに叩くとバラバラになりがちです。「よーっ!」の後に半拍〜一拍の間を意識しましょう。
③ 声が通る位置から行う
宴会の終盤は、会場がざわついていて声が通りにくくなります。可能であれば前の方・中央に出て、マイクを使って行うとスムーズです。
④ 手は頭の少し前あたりで
胸の前より少し高め、顔の前〜頭のあたりで叩くと、全員が揃って見えやすく、写真映えも良くなります。
ギガセットWiFiを詳しく見てみる ▶
👉 利用者の声
「契約も解約もいらないし、端末オンですぐ使える。月額ゼロで必要なときに必要な分だけ、これ本当に便利すぎ!」
まとめ:一本締めと三本締めの違いを理解して、スマートに場を締めよう
最後に、もう一度ポイントを整理します。
- 一本締め(=一丁締め)は、一連の拍手を1回だけ行う簡略版。カジュアルな場や少人数の会に向いている。
- 三本締めは、その一連を3回繰り返し、最後に一本締めで締める正式なスタイル。式典や披露宴などフォーマルな場に最適。
- 関東では形式が重視され、関西では比較的自由なスタイルも見られる。
- いずれの場合も、掛け声と「間」を意識し、事前に簡単な説明を添えると、きれいに揃って気持ちよく締められる。
一本締めと三本締めの違いを理解しておけば、「締めのご挨拶をお願いします」と突然振られても、落ち着いて進行できます。次の宴会やイベントで、ぜひ実際に使ってみてください。