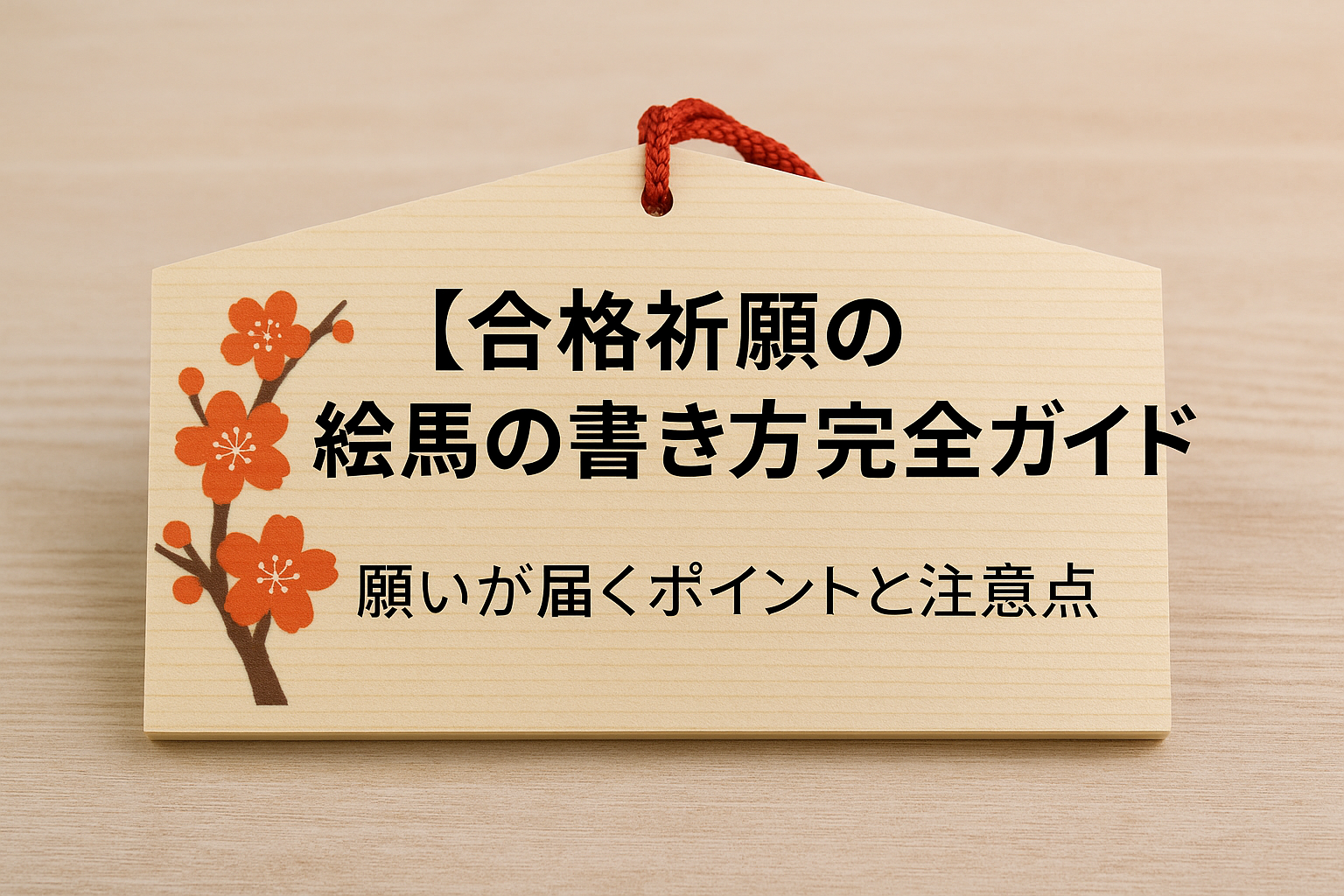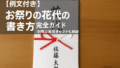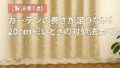【例文付き】合格祈願の絵馬の書き方完全ガイド|願いが届くポイントと注意点
はじめに
受験シーズンになると、多くの人が神社やお寺で「合格祈願」の絵馬を奉納します。しかし、いざ書こうとすると「どんな文章にすればいいの?」「名前や日付は入れるべき?」と迷ってしまうこともあります。
絵馬はただの木の板ではなく、神様や仏様への手紙のような存在です。書き方や言葉選びを少し工夫することで、気持ちがより届きやすくなります。
この記事では、合格祈願の絵馬の意味、正しい書き方、願いを込めるコツ、実際に使える例文集まで詳しくご紹介します。初めての方でも自信を持って奉納できるよう、マナーや注意点も解説しますので、ぜひ参考にしてください。
合格祈願の絵馬とは?
絵馬は、古くは「馬」を神様に奉納して願いを叶えてもらう風習から生まれたものです。馬は神様の乗り物とされ、祈願の際に馬を奉納することで神様に願いを届けていました。やがて、本物の馬の代わりに木の板に馬の絵を描いたものを奉納する形になりました。
現代では、馬の絵に限らず、願い事に合わせたイラストやデザインの絵馬も多く、特に受験シーズンには「合格祈願」と書かれた絵馬が人気です。
合格祈願の絵馬は、
・神仏に対して合格を誓う場
・努力を形にして心を引き締めるツール
として、多くの受験生やその家族に利用されています。
絵馬を書く前に準備すること
1. 願いを明確にする
「合格しますように」だけではなく、試験名や学校名を正確に記載することが大切です。具体的にすることで、願いがより明確になり、自分の目標意識も高まります。
例:
・令和7年度 ○○大学 ○○学部 合格
・○○資格試験 一発合格
2. 肯定的な表現にする
否定形の「落ちませんように」は避け、「合格します」「受かります」と前向きに書きましょう。言葉には力があるため、ポジティブな表現の方が自分のモチベーションにもつながります。
3. 感謝の気持ちを込める
お願いだけでなく、「ありがとうございます」「感謝します」といった感謝の言葉を加えると、礼儀正しい印象になり、より誠意が伝わります。
合格祈願の絵馬の正しい書き方
表面
- 願い事:試験名、学校名、年度を明確に書きます。「○○高校に合格します」「○○資格に合格します」と言い切る形が望ましいです。
- 名前:フルネームが基本ですが、プライバシーが気になる場合は名字のみやイニシャルも可能です。
- 日付:奉納日を入れることで、その時の気持ちを記録できます。
裏面
裏面は補足的に使います。表面で書ききれなかった想いや、家族や友人への感謝の言葉などを入れると良いでしょう。
筆記具
神社やお寺で用意された油性ペンを使用します。消えるペンや鉛筆は避けましょう。
願いが叶いやすくなるポイント
- 肯定形で書く:「合格します」と断言すると、自己暗示にもなり、前向きな気持ちを保てます。
- 具体的に書く:「第一志望」だけでなく、正式名称を入れることで願いが明確になります。
- 感謝を添える:「ありがとうございます」「感謝します」で締めると、誠実さが伝わります。
- 丁寧な字で書く:字の美しさよりも、心を込めて書くことが大切です。
合格祈願の絵馬の例文集
受験生本人の場合
- 令和7年度 ○○大学 ○○学部に合格します。日々の努力を実らせます。ありがとうございます。
- 第一志望の○○高校に合格します!支えてくれる家族や友人に感謝します。
家族からの場合
- 息子○○○○が○○大学に合格しますように。日頃の努力が報われますようお守りください。
- 娘○○○○が志望校に合格しますように。ありがとうございます。
友人からの場合
- ○○ちゃんが第一志望の○○高校に合格しますように!一緒に春から通えることを楽しみにしています。
グループでの場合
- ○○ゼミの全員が○○資格試験に合格します!お導きいただき、感謝いたします。
やってはいけないNG例
- 否定形で書く:「落ちませんように」ではなく、「合格します」にしましょう。
- 漢字間違い:学校名や資格名は正確に。誤字は失礼になります。
- 落書きやふざけた内容:神聖な場所では控えるべきです。
絵馬を奉納するときのマナー
- 順序:本殿でお参り → 絵馬に記入 → 絵馬掛けに奉納
- 奉納場所:指定された絵馬掛けに丁寧に掛けます。
- お礼参り:願いが叶ったら、改めて感謝の気持ちを伝えに行きましょう。
ギガセットWiFiを詳しく見てみる ▶
👉 利用者の声
「契約も解約もいらないし、端末オンですぐ使える。月額ゼロで必要なときに必要な分だけ、これ本当に便利すぎ!」
まとめ
- 絵馬は具体的・肯定的・感謝の気持ちで書くことが大切です。
- 学校名や試験名を明記し、誠意を込めて丁寧に書きましょう。
- マナーを守って奉納することで、気持ちがさらに引き締まります。
合格祈願は努力の後押しをしてくれる大切な行事です。この記事を参考に、自分の思いを込めた絵馬を奉納し、合格への一歩を踏み出してください。